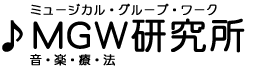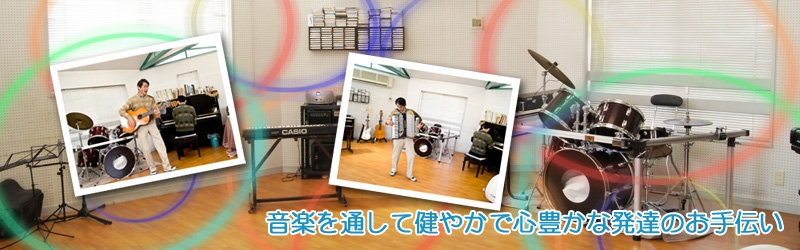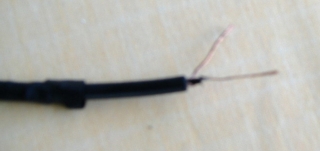■ エレキベースを使おうと思い、
アンプにつないだが、音が出ない。
先日のセッション中の事だ。
過去の経験から、
ベース内部に取り付けられている、
電気部品間の断線によるものではないかとあたりをつけた。
今までに何回もこんなことがあり、
その度にベースの内部を開けては、
自分で修理をしてきたからだ。
・・・修理の時間が取れず、数日がたった。
■ 昨日(4/21)のセッションで、
クライアント持参のエレキギターを、
アンプにつないだが音が出ない。
(ギターをやりたくて来ているクライアントもいる)
問題はギターではないだろうとあたりをつけ、
シールドを変えてアンプにつないでみた。音が出た。
そのシールドでベースとアンプをつないだところ音が出た。
そこで、ベースの音が出ないのは、
その時つないだ、シールドにあると分かった。
■ 音の出ない時はその原因を、
ベースなどの楽器自体、アンプ、シールドなどと順に考えてみるのだが、
今回はベースそのものだと思い込んでしまっていた。
思い込むと見えなくなる。
クライアントさんのことも、
そのような思い込みで、
見えにくくならないように気を付けたいものだ。
■ 修理の経過
① シールド
② 断線の部分
③ 被膜をはがす
④ ハンダ付けをする
⑤ 無事、終了・・・音が出た

■ 因みに、修理をしようと道具を出したが、
ハンダが無くなっていた。
いそいでホームセンターで買ってきた。
ハンダゴテは、高校生の時から使っている年代物だ。